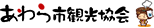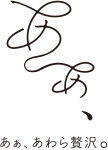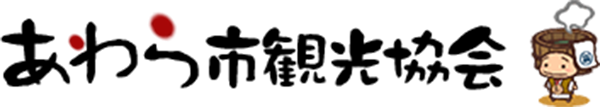プロ野球ファンであれば、
1995年のNOMOフィーバーを覚えておられるだろう。
近鉄バファローズを退団した野茂英雄投手は、
1995年2月8日、ロサンジェルス・ドジャースとマイナー契約を結び、
5月2日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でメジャーデビュー。
31年ぶり2人目の日本人メジャーリーガーとなった彼は、
「トルネード投法」をひっさげ、
6月24日のジャイアンツ戦ではなんと日本人初の完封勝利を記録。
日米で「NOMOマニア」と呼ばれる熱狂的なファンが現れた。
その奇跡のNOMOフィーバーを
もしかしたら最も近くで見ていたと言えるかもしれない人物が、
今回のあわら贅沢な人、寺尾博和さん。
日刊スポーツの記者として
近鉄時代から野茂さんを取材していた寺尾さんは、
野茂さんとともに渡米して彼のメジャー挑戦を
つぶさに取材し続けたのです。

―――寺尾さん、今日はよろしくお願いいたします。
寺尾:故郷あわらのためなら何でも協力しますよ(笑)
―――本業は新聞のスポーツ記者をされてますが、関西のテレビやラジオでも時々お見かけします。
寺尾:2004年からABCテレビの「おはようコール」という番組に出演させていただいております。あと、ABCラジオの道上洋三さん(ラジオパーソナリティー)のラジオ番組にも出演していまして、実は今日も寝てません。朝が早い番組なので深夜4時とかに局入りしないといけないんです。で、いまから甲子園でナイター取材があるし。もう無茶苦茶な生活です(苦笑)
―――なにかのインタビューで「休日がない」とおっしゃってました。
寺尾:いまは日刊スポーツ編集委員で、プロ野球取材はもちろん、メジャーリーグ、WBC、オリンピックにも出掛けるし、テレビやラジオでコメンテーターもさせていただいてます。
―――生まれも育ちもあわら市で?
寺尾:はい。旧芦原町で、あわら温泉のど真ん中で生まれてるんです。だからずっと、LOVEあわら、ですね。うちの本家はもともと温泉旅館で、ちなみに弟は温泉街のなかで蕎麦屋を営んでます。おろしそばが名物ですが、かつてはご来福された昭和天皇もご宿泊の際にお召し上がりになったという由緒ある蕎麦屋です。芸能人もよく立ち寄られますよ。

―――こどもの頃の思い出は?
寺尾:ぼくが小さい頃の温泉街というのは、浴衣着て丹前をはおったお客さまたちの下駄がカランコロンと鳴る音が毎日のように響いていました。大勢のお客さまで賑わっていた印象が強く残っています。「関西の奥座敷」という言葉そのままの雰囲気がありました。小さい時から毎日温泉に浸かってたから、ほら、肌ツヤツヤです。やはり温泉が原風景ですね。芦原祭では、桜山車、人形山車が街を巡って華やかでした。山車には芸者衆が乗り込んで、そこにぼくらも乗せてもらって、チン・トン・シャンってね、街を練り歩く。芦原節、という歌がありましてね。
(ここから歌い出す寺尾さん)
花の「チョイトナ」 しずくかぁ
芦原の いで湯「チョイ チョイ」
すいた同志が 桜色
ほんと うれしわねぇ♪
ていう、こういう歌で四季を綴っていくんです。
―――素晴らしい、粋な歌ですね!

―――地域のつながりもやっぱり濃かったですか、昔は?
寺尾:それは今も変わらないと思いますよ。今年(2018年)2月の大雪で、国道にたくさんの車が数珠つなぎで止まってしまった時も、地域の人たちが総出でおにぎりなど食料を一台一台に差し入れしたという話がありましたし。今や福井県は、全国都道府県のなかでも「幸福度ナンバーワン」と位置付けされていますから。
―――あぁ、まさに「あわらむすび」ですね。
寺尾:にじみ出る温かさ、といいますか。そういったものが幸福度の高さに表れているんじゃないですかね。
―――ずっと野球をされてたんですか?
寺尾:小中高、そして大学まで、ずっと。
―――きっかけは?
寺尾:あわらの中心街に舟津公園ってあるんですが、そこでおやじとキャッチボールをしたりしてるうちに、野球の魅力に取り込まれていったという感じですね。
―――日刊スポーツに就職されたきっかけは?
寺尾:大阪体育大学でも野球部に所属していました。副キャプテンで、阪神大学リーグでベストナインにも選ばれた。だから本当は母校(三国高校)に帰って野球部の監督をやりたかったんですが。
―――あ、そうなんですね。地元に帰ろうとされてたんですね。
寺尾:ええ。あわらLOVE、地元に愛着がありましたから。体育教師になろうと思ってましたが、採用もなくて。結局、大阪で、全然目指してたわけでもないのに新聞記者になりました。でも、スポーツにたずさわり続けたい気持ちは確かにあったなぁ。
―――日刊スポーツに就職される方って、体育会系の方が多いんですかやっぱり。
寺尾:みなさんにそう言われるんですけど、逆に少ないんですね。文系の人が多くて、「体育学部体育学科」卒なんていうのは珍しいです。1986年の入社から、ぼくはずーーーっと現場にいるんですよ。それもかなり珍しくて。現場の第一線にいるスポーツ記者で、いちばん長いキャリアかもしれません。
―――体育会ご出身というのが影響してますか?
寺尾:もちろんアマチュアとプロの違いはありますが、例えば、ホームランを打った時の気持ちよさだったり、エラーした時の悔しさだったり、そういったものが記事の行間ににじみでるのは、有利かもしれませんね。体育会にいたのは。三国高校でも、やさしく、厳しく、育てられましたから(笑)
―――1995年から、野茂選手の取材でいっしょに渡米されてます。
寺尾:当時、スポーツ記者の海外出張いうのは、オリンピックか、ウィンブルドン・テニスの取材ぐらいで、みんな経験なくて、野茂選手自身も、われわれ取材陣も手探り状態でした。インターネットも無いし。世界地図を一枚わたされて「行ってこい!」の状態ですからね。飛行機やホテルの手配も電話で。全米各地を転戦しますから、それに付いて回らないといけないんです。「明日はフィラデルフィアだ」「フィラデルフィアはわかるけど、球場はどこにあるの?」みたいな繰り返しですから。あの野茂選手から「いま、そこにあるものを食べないと、生きていけない」と打ち明けれたくらいですから。サバイバルですよね。原稿はFAXでしか送れないし、カメラマンはホテルのバスルームに暗室をつくって写真を現像してましたよ。そんな経験をしてきたから、今は何も怖くないですね。

寺尾:とにかく毎日、スポーツ新聞の一面記事が野茂なんです。すごいですよね。1年目からオールスターに出場するどころか、ナショナル・リーグの先発をしましたし、新人王、ノーヒットノーラン…。彼がメジャーに風穴を開けなかったら、イチローも松井もダルビッシュも大谷も、無かったかもしれないわけで。
―――野茂以降の日本人メジャーリーガーもたくさん取材されてます。
寺尾:ちょっと自慢になっちゃうけど、野茂さんとか新庄さんとかは、特に取材をした思いが強いです。

―――そこまで選手から信頼されるのは何故でしょう?
寺尾:何故かはわかりません。一流選手にありがちなんですけど、だいたいメディア嫌い。そこにどう食い込んでいって特ダネを聞き出すかが我々の醍醐味なわけで。「なぜ野茂が完封できたか」「なぜ新庄はあんなに走れるのか」を深堀りして、その裏側を見つけないと読者は読んでくれませんからね。
―――そのコツは?
寺尾:よく言われるんですけど。スキージャンプの高梨沙羅さんがワールドカップで連勝した時に、「なんでこんなに強いんですか?」って記者から聞かれて、彼女は「人間力だと思います」って答えたんです。ジャンプ力とかじゃなくて、人間力。
―――あんなに若いのに。
寺尾:ぼくに人間力があるかどうかは別にして、「人と人とのつながり」ってそういうものじゃないですかね。テクニックじゃないですよね、たぶん。話術がうまいから選手や監督が本音でしゃべってくれるかっていうと、そういうもんじゃないですね。心がけてるのは「真を書く」。真実を尽くして、真心を込めて書く。ということですね。

スポーツ記者としてずっと第一線で取材を続けておられる、寺尾さん。
活躍の舞台は日本にとどまらず世界ですが、
なんと、持ち前のバイタリティをいかして
「お弁当開発」や「スイーツ開発」の監修も手掛けておられます。
特に、2011年の日刊スポーツ×オリジン弁当×パナソニック・パンサーズの
コラボプロジェクトでは、ソースカツや福井梅など福井県の食材を
ふんだんに使った“特製日の丸弁当”を開発して好評だったそうです。

―――寺尾さんの人間力やコミュニケーション力の原点は、あわら温泉での幼少時代にあったりするのでしょうか?
寺尾:あえて言うのではれば、「人が好き」。いろんな人が行きかっていた温泉街で、いろんな人を見ていたから。2月の節分におじいちゃんが裃姿で豆をふるまったり、お正月には芸者衆がお年玉くれたり、お相撲さんや、お忍びで有名人もよく来られて、弟が継いだ蕎麦屋に名優の宇野重吉さんが常連でいらしたり、本家の旅館を訪れた萬屋錦之助さんといっしょにお風呂に入ったり。物心の付かない幼少時からいろんな人と会話してたんでしょうね。
―――あわらがこうなったらいいな、と思われることは?
寺尾:北陸新幹線の停車駅になるとか、それに伴って観光客を増やして活性化させよう、だけではダメだと思うんです。地域経済だけではない何かで「日本一のあわら市」「世界に発信できるあわら市」になるグランドデザインを行政だけでなく市民も一緒に描いてほしいですね。私にとってはやはり「あわら市=温泉」なので、昔みたいな風情があるあわら市に原点回帰できないかな、といつも思ってます。しょっちゅう帰省しています。何かきっかけがあって、お役に立てれば、地元で働きたいな、なんて思うことありますよ、今でも。